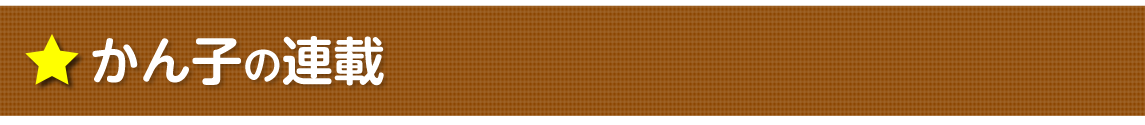LGBTQの本棚から 第15回 「夫夫円満」
今回紹介するのは
「夫夫円満」
「夫夫」とかいて「ふうふ」と読みます。
文字通りゲイカップルのお話です。
もっとも、まだいまは、ふうふ、で変換すると夫婦しかでてこないのですが……。
この本は実在するゲイカップルが体験した実話です。
2人は職業の都合で様々な国にいきます。
いくつかの国で2人をカップルとして認めてもらえただけでなく、他のストレートの夫婦と同じように扱ってもらえたことが何より嬉しかったと語っています。
2人が自分たちを「夫夫」だと表現することは自分たちが特別な存在ではなく、見えない存在でもなく、ごく普通であることを意味しているのでしょう。
彼らの話を通してセクシュアルマイノリティが辿ってきた歴史を知ることもできます。
たとえば、80年代後半はLGBTQの、特にゲイにとって試練の時代だった、という話がありました。
HIV(通称エイズ)が多くのゲイの間で流行したからです。
今でこそ、男女間の性交渉や輸血でも感染する病気だと認識されるようになりましたが(結局ウィルスが原因だったのですから)
当時は
「ゲイのかかるガン」
だとまでいわれていたそうです。
原因がわからず、感染も防げない……。
有効な薬もなく、致死率がとても高い……。
そういう未知の病気への恐怖がゲイへの恐怖にすり替わり、偏見や差別が激しくなったというのですが、原因が解明され、コントロールできるようになると、偏見や差別も徐々に社会から消えていったそうです。
知らないから怖い、怖いから遠ざけたり攻撃したりする……。
無知が、恐れを助長するわけですね。
これはセクマイだけではなく、いろいろな障害を持つ人々や、有名でない難病の人々にもあてはまることでしょう。
そうして誰にだって、事故や病気によってそういう少数派、という立場になる可能性はあるはずです。
自分だけじゃなく、家族や友だちがなる可能性も……。
だからこれはそういう一部の人たちの問題ではなく、全員の問題なのです。
この多数派がいいんだ、少数派は嫌だ……の代表として、日本には
「みんなと同じでなけれはならない」
という強いプレッシャーがあります。
日本ではおそらくどの学校でも、どんな生徒にとっても「人と違うということ」
が最悪なのだ、という話もこの本にはでてきます。
これ、本当に不思議なのですが、日本人は”人と違う”ことをとても恐れますよね。
実は、僕もそうでした。
小学生の時の僕はおとなしく、人と違うことや叱られることがとても嫌でしたから、そうならないように、いつも回りを見ていたものです。
ですからその頃の自分は漠然と、将来は小中高大と無難に進学して、公務員になって、そのまま平凡にこの町で生きていくんだろうなぁ、と思っていました。
でもセクマイを自覚してしまったあたりから、どう転んでも“人と違わない”でいることは無理になり、徐々に考え方は変わっていきました。
ですから”人と違うこと”を怖がる気持ちもわかりますが、違ったからといって、じゃあどうだったろう、と考えると、それほど大きく変わったことはなかったように思います。
確かに“人と違って”苦労したことはありました。
でも、結局、僕は僕だっただけだったからです。
最後に
『2020年の東京オリンピックは日本の存在感を世界にアピールする絶好の機会となるでしょう。一方で、すべての社会問題がオリンピックを機に表面化するともいえます。』
という言葉がこの本にありますが、僕もそう思います。
オリンピックは様々な国と文化が混ざり合う場でもあるので、同性婚を許可している国や、日本よりセクマイに対してオープンな国と交流することにもなりますよね。
そんな国の人たちから見たら、日本は結構閉鎖的でセクマイに対して寛容ではないように見えると思います。
そういうマイナスな面はメディアに取り上げられやすいし、議題にもしやすいです。
日本で扱われなくても、海外で話題にされたら日本でも考えざるをえなくなりますよね?
以前何かの選挙の時に(政権交代だったかな?)党別議員別に
「セクマイについてどう思うか」
という質問をした結果がセクマイの間で話題になっていましたが、ある党が特にひどく
「セクマイに人権はない」といった発言をする議員がいたほどでした。
しかしこのことは当時、なんの問題にもされませんでした。
大手のメディアにとっては、これはみんなの共感を得られそうな話題ではなかったわけです。
しかし世界的な話題になればそうはいかなくなるはず……。
ということでLGBTQ関連の問題は間違いなく東京オリンピックを機に表面化してくると思います。
そのとき、声をあげてくれる人が多いほど、いい方向に進むでしょう。
ですから、そういうことをどこかでみかけたら、サポートしてくださると嬉しいです。
よろしくお願いします。
とまあこのように、社会問題を考えるところまで連れて行ってくれるのが「夫夫円満」です。
ぜひあなたの図書館に1冊いれてみてください!
2017/07/31