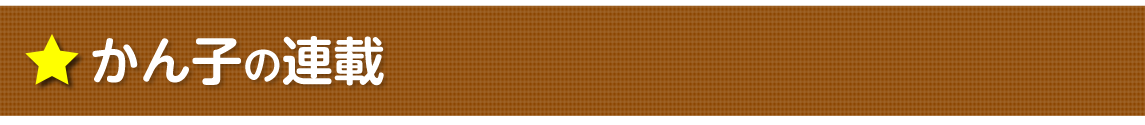☆楽しい学校図書館のすぐに役立つ小話☆彡【司書は椅子に座ってピッとやるだけの人じゃありません。学校司書は忙しいんです。・3-7】
学校司書の桜李桃梨(おうりとうり)さんからの寄稿をご紹介していきます。
小話とは言えない😅、学校司書さんの忙しい日々をぜひご覧くださいませ~
☆ ☆ ☆ ☆ ☆
3-7 本を読む
図書の授業のメインの一つに「子どもたちに本を読む」があります。
私は図書の時間の最初の10分は、しらべかたの授業を一つするか、本の紹介(ブックトーク、といいます)をするか、本を読むか、をするようにしています。
子どもたちはバタバタ入ってきて返す本をカウンターに置くと素早く決められたスペースに集まります。
そこでなにがしか本を紹介されて、それから自分の読みたい本に散っていく、というわけです。
その時間内に読めるもの、なので、ほとんどは絵本になりますが、長編の一部や、動物図鑑の1ページ、元素の本から一つだけ、というときもあります。
世界的なニュースがあったときは、それに関連する本を紹介したり、その一部を読んだり、地図を見せたり、というときもあります。
とりあえず、どこで?
は正確に把握しといたほうがいいですから。
最近はそうやって使える本が色々出てきて本当にありがたい限りです。
みんなが落ち着いて一度読み出すと針を落としても聞こえる、かもしれないほど静かになりますので、私はその間にカウンターに積まれた本の返却手続きをし、返された本をブックトラックに乗せ(そうしておくとたいていそのままその日のうちに貸し出されますので、棚に返す手間が省けます。棚に返すのは一日の最後に一度だけやります)授業の最後の10分に貸し出しをするためにスタンバイするわけですが、その間にもちろん、リクエストを受け付けたり相談にのったりもします(そのあいだにとっとと本を借りていく人もいますので、全然ひまではありません)。
よく、何を読むのですか?と聞かれるのですが「本を読む」といっても色々なパターンがあり、先生がたに「次の単元でこれをやるのでプレになるものを読んでほしい(たとえばダイズの加工食品の話をやる前に、ダイズがどうやって大きくなるのか、という植物としての視点の本を読む)というときもあれば、このテーマの本を、と学習しているテーマを膨らませる本を要求されるときも、校内行事で平和週間なので、この週は「平和がテーマの本を」
と依頼されることもあります。
図書館から行事にあわせて、七夕とかお月見、のような季節ものを読むこともあります。
気持ちが荒れてるクラスには共感できそうなもの、転入生が来る、と決まったクラスには引っ越しすることになって心細くなっている子の本を読んだり……(これは担任の先生に依頼されました)。
でもそれ以外は、こちらが聞いてほしい本ではなく、といっても、私には別段、ぜひともこれを聞いてほしい!というような本はないのですが、子どもたち自身が面白い、と思ってもらえるようなものをなるべく選ぶのですが、これが難しい。
図書館の常連さん以外は、ほぼ週に一度お目にかかるだけだったりする人もいるので、今の傾向、を素早くとらえなければなりません。
案外そっぽ向いて、聞いていないように見える子が実はすごく良く聞いていることもあって驚かされることが多いです。
5年も前に一度だけ読んだ本のことをふいに、これ読んでくれたよね、と言われたり……。
そのときは、よく覚えてたね、といったら、だって面白かったから、といわれて二重に驚いたり。
だって、そのときは本も見てくれないし、全然聞いてるようには見えなかったんですから。
でも、耳はこっち向いてたんですね!
とにかく全員にお目にかかれるのはこの時間だけですので、毎回全身を耳にして情報収集をします。
毎年同じ学年に同じ本を読めばいいかというと、やはり時代は動いていくので、特にこの5年ほどはその動きが急激なので、前使えてた本が使えなくなることが増え、きりきり舞いしています。
と思えば50年も前の本がいきなり復活したり、正直ものすごく大変なのですが、そのぶん、見返りも多い仕事です。
そうしてこういうところが公共図書館とは違う、学校司書の醍醐味だったりします。だって公共の司書さんは、毎週同じお客さま相手に本を読むことはありえないでしょうから。
6年間、変化と成長を見ていられる、というのは学校図書館の特権だと思います。
そうして本を読むには準備が必要です。
本選びはもちろん、下読みも必要です。本を読むのは“演劇”の一つです。
内容を読んで読解し、再構成してそれを声にのせなくてはなりません。
朗読ほど厳密にはやりませんから朗読譜までは作りませんが、お客様に聞いてもらうのですから読み方を考え(カットするときも考え)何回か読んで練習します。
そして準備体操も必要です。
本を読むのは肉体労働……、体を使うので、体が硬くなっていたりこわばっていたりすると声は出ません。
音というのは空気の振動です。
空気を震わせることができれば音は伝わる……。
たとえばティンパニーを叩くとティンパニーは震えて音を響かせますよね。で、それを止めるときにはどこかを触ればいい。
振動を止めると音は止みます。
声も同じ。
人間は体中の骨、内蔵、筋肉、皮膚、を震わせて声帯で作った声を増幅させて大きな声を作るのですから、体のどこかが固くなっているとそこで声は止まるのです(これはボイスの先生の受け売り。ついでにいうと、話し始める2時間前には最低起きてなくてはならないそうです)。
なので毎朝起きたら軽くストレッチをして体をほぐし、顔の体操もし、声も出してみます。
なのでたいてい学校にいくあいだの車の中では音楽を聞いているか歌っていることが多いです。
これは趣味ではなく、本を読むための準備体操なのです。
2025/02/20 更新