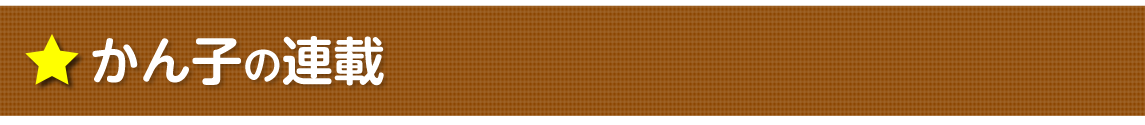☆楽しい学校図書館のすぐに役立つ小話☆彡【司書は椅子に座ってピッとやるだけの人じゃありません。学校司書は忙しいんです。・3-11】
学校司書の桜李桃梨(おうりとうり)さんからの寄稿をご紹介していきます。
小話とは言えない😅、学校司書さんの忙しい日々をぜひご覧くださいませ~
☆ ☆ ☆ ☆ ☆
3-11 別置
公共図書館と学校図書館の本は、NDC(日本十進分類法)というやりかたで分類されてますが、それだけでは困るときは、テーマで本を集める“別置(べっち)”という分類もします。
別置は、棚のなかでやるときもありますが、テーブルを使って“展示”するときもあります。
たとえば離婚問題の本は法律、女性問題、家族問題、危機管理、ドキュメンタリー、はたまた児童文学のなかにも物語の形で混在していますが、普段そうやってバラバラに置いてある本を“離婚”というテーマで
いつもの置き場所から引っ張り出して、こういう本もありますよ、という宣伝をするわけですね。
毎年、大河ドラマや朝のテレビ小説が始まれば、どこの公共図書館でもその関係のテーブルを作ります。
そうしてこの展示は放送が終われば終わり、の期間限定別置ですが「三国志」なんかはもう永久別置だな、と思います。
もう何十年もたつのに、一向に人気が衰えないんですよね。
ここまでいままでのなかにあったっけ?
その別置展示のなかの一つに
“季節の展示”
というものがあります。
その時の季節にあわせてサイン(「クリスマス」とか「七夕」とかのパネル)といっしょにそのテーマの本を並べるのですが、季節にあわせてテーブルクロスの柄や色を変えたり、本以外の飾り物も置いたりするわけですね。
うちの図書館では入口近くに季節の展示のテーブルがあり、通りすがりに目に入るので、子ども達もつられて入ってきてくれるし、時には先生がたも立ち止まって子ども達と話しながら一緒に見ていることもあり、この、季節の展示はなかなか好評です。
毎回
「お!先生変わったね!」
と、ちゃんと気がついていっていってくださる先生も
「あら、こんな本、あったのね」
とか
「今度クラスで読むので借りていいですか?」
と借りていかれる先生もいらっしゃいます……。
先日も副校長先生が通りすがりにふらっと図書館に入ってこられて
「あら、この図書館はいつも季節を感じられていいわねぇ♪」
と展示していた本を手に取られていました。
図書館、あまりいらっしゃらないな~、と思う先生がたでも、案外ご存知だったりするのがこのコーナーです(季節ものは効果的ですが、この展示はテーブル一つにとどめておくのがコツだと思います。部屋じゅうを七夕飾りで飾ってるところを見たことありますが、逆に興ざめでした。図書館の飾りは本を引き立たせないといけないと思います)。
この“展示”というノウハウは、もちろんお客さまに本を宣伝するためなのですが、もう一つ、司書が図書館の蔵書をチェックするためのテクニックでもあるのです。
来年の干支の本、あるかな~、とか、9月は紅葉の展示にしよう、というようにテーマで本を確認し、足りない本は発注し、蔵書の充実を計るわけですよ。
公共図書館などだと、いま手薄になっているところ、たとえば、ブラックホール発見されたけどうちは弱いなぁ、というときには、わざとそれを展示テーマにして、調べたり勉強したりして必要な本のリストを作り、本を揃えます。
そうすればそのジャンルに関しては基本の本は揃い、あとはあまり考えなくても新刊が出たときに買い足していくだけでしばらく保つ、ようになるからです。
で、展示はだいたい半年前から準備を始めるのが普通です。
そのテーマを勉強し、必要な本をリスト化し、発注し(注文ね)本が来たら装備して登録しなくてはならない……その一連の作業をするのに半年くらいはかかるからです。
関係する本を読んだり資料を集めたり、研究するのはたいてい時間外、にやるので思ったより時間を取られます。
学校はそこまで凝りませんけど(凝りたいけどそこまでお金がないので)それでも本が来るのに最低一ヶ月はかかりますから、2ヶ月前くらいから準備しないと間に合いません。
私は季節の展示本だけは、一年分この月にはこれをしよう、と計画して今持ってる本をチェックし、5月にまとめて注文してしまっています。
そうなると、もちろん、今年出る本はそこには入りませんので、季節になったときに気をつけて、入れたい本があったらメモしておきます。
そのとき買っても展示には間に合わないので、まとめて次の年の6月に買うのです。
前の前の学校で一年目のときにクリスマスに本を飾ろうと思ったら、なんと、クリスマスの本が一冊もなかったことがあったのです。
あわてて調べたら、お正月の本も雪の本も氷の本も節分の本も、つまり冬の本がゼロ……。
6月に、年に一回しか本を買わなければ、気をつけないとそうなってしまいます。
日本の文化には季節感、がありますから、ハロウィンが終わらないと本屋さんにクリスマスの本は並ばないのです。
なのでそれ以来、春に調べてまとめて注文しておくことにしたのです。
季節の展示の本も貸し出しをします。
クリスマスの本などは特に人気で、低学年だけでなく高学年も
“クリスマスの絵本って、好きなんだよね~”
といって見ているほどです。
高学年はたいてい絵本は借りて行かないで見ていくだけなので、借りてもらえないと貸し出し冊数は稼げないのですが、子どもたちには日頃から借りなくてもいいから、ちょっと見てってね~、と言っています。
はじめから終わりまで読まなくても、借りなくても、ちょっと読むだけでも子ども達の脳には残る、という話をどこかで読んで以来、毎年オリエンテーリングの時や何かの時には積極的にこれは言うことにしているのです。
「借りなくてもちらっと見てみてね~」
って……。
だって、図書館って、このちら見には絶好の場所なんです。
本屋さんは、そうそう立ち読みはできない……。本屋さんの本はそこの人が一生懸命勉強して注文して集めた、そこにその本が並んでいるという事自体が、知的財産なのです。
それをお金を払わないでただで読むことは、盗むのと同じですよね?
そうしてもいいですよ、といってる書店もありますが、買おうと思って吟味するのと、ただ読みは違うわけですから。
そこへいくと図書館は気兼ねなく、いくら立ち読みしてもいいのだし、お金もかかりません。
本当に、いくらでも読んで!
と思います。
2月のバレンタインフェアも人気です。
バレンタインの時は、とっておきのチョコレート柄のテーブルクロスをひいて、チョコレートの作り方の本やお料理関連のお話なんかもたくさん並べますが、これもどんどん借りていかれます。
バレンタインは1月15日にお正月が終わったらすぐにセットします。
最近は、まだ1月なのに借りていく人が増えてきたのです。
昔は駆け込みで14日当日に、貸して!といってくる子もいたくらいなのですが、今の子どもたちはなんというか、やることがスマートだな、と思います。
最近は友達にチョコを渡したり、一緒に作るのが流行りのようで
「〇〇ちゃんとチョコレート作るんだぁ~」
と言って借りていく子が1月半ばから現れるのです。早いなぁと思って聞くと
「だって2月に入ったら借りたいチョコレートの本なんて、なくなるもん。早めに借りておくの!」と……。
賢い!
安くて易しい本をかなりたくさん揃えている方だと思うのですが、それでもあらかたなくなります。
ハロウィンのときには、サインや本と一緒にあの大きな橙色のかぼちゃをかざったところ、大評判になりました。
子ども達がさわりながら
「これって本物!?食べられるの?」
と聞いてくれました。
前に給食担当の先生とお話してたら、最近は季節の行事をするご家庭も減っているので給食では季節を感じられるメニューを意識して取り入れているのだそうです。
こうやって、季節の展示を変えるたびに
「先生、もうこんな季節なんだね~」
という人が何人もいます。図書館は公園の木々ほどではないですが、それでも季節の移ろいを感じられる場所でありたいと思うのです。
2025/04/24 更新